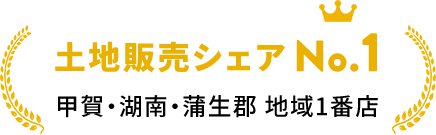施工実例・お客様インタビュー
GALLERY & VOICE
不動産売却時の減価償却とは?計算方法と税金の注意点を徹底解説
-
不動産売却における減価償却の基本知識
減価償却の定義と重要性
建物は年月とともに価値が減少します。この価値の目減りを会計・税務上で費用として計上する仕組みが減価償却です。不動産を売却する際、所得税の計算では「取得費」を差し引いて譲渡所得を求めますが、取得費には減価償却費を控除した残存価額しか認められません。つまり減価償却は売却益に直結し、納税額を左右する極めて重要な要素なのです。びわこホームでは売却前に減価償却の累計額を精査し、想定納税額を試算したうえで最適な売却スケジュールを提案します。
減価償却が必要なケースとは
居住用でも事業用でも、建物を所有する限り減価償却は発生します。賃貸に出している場合や青色申告の事業資産であれば、毎年所得から減価償却費を経費算入してきたはずです。その累計額の大小が、売却時の課税所得を大きく変えます。 -
減価償却の対象となる不動産の種類と計算方法
事業用不動産の減価償却
店舗や賃貸マンションなど収益物件の減価償却費は毎年の節税に直結しますが、売却時には「取得時価格−累計減価償却費」が取得費になるため、長期保有ほど譲渡所得がかさみます。当社は売却前後の法人税・所得税・消費税まで一体でシミュレーションし、手取り最大化を図ります。
非事業用不動産の減価償却
自宅は通常、減価償却費を毎年経費化できませんが、売却時には法定耐用年数に応じた“みなし減価償却”が強制適用されます。たとえば木造住宅(耐用年数22年)を30年保有して売却する場合、取得費はほぼゼロに近づき、売却価格の大半が課税対象になる点に注意が必要です。
法定耐用年数の影響
耐用年数は構造によって異なります。木造22年、鉄骨造34年、RC造47年などが国税庁の定める基準です。中古で取得した場合は残存耐用年数を見積もる特例があり、計算を誤ると税務調査で追徴を受けるリスクがあります。びわこホームでは固定資産台帳や登記簿から構造を確認し、正確な耐用年数を用いています。
減価償却費の具体的な計算方法
定額法では「取得価額×償却率」で毎年同額を費用計上します。定率法は「期首帳簿価額×償却率」で初年度の費用が大きく、徐々に減少します。平成28年以降、建物は定額法が原則となったため、使用する償却率の取り違えに注意してください。
減価償却の償却率について
償却率は耐用年数に対応して国税庁が公表しています。例えば耐用年数22年の木造住宅なら償却率は0.046、鉄骨造34年で0.030などです。びわこホームでは国税庁改正情報をリアルタイムで反映し、計算根拠も添付して税務リスクを回避しています。 -
譲渡所得税と減価償却の関係とシミュレーション
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得=譲渡価格−取得費−譲渡費用。取得費が減価償却後の残存価額で計算されるため、長期保有物件ほど課税所得が増える構造です。
減価償却が譲渡所得税計算に必要な理由
減価償却費は資産が消耗して目減りした分とみなされ、「もう回収済みのコスト」と扱われるため取得費から控除されます。認識漏れがあると、税務調査で追徴課税と延滞税が発生します。
減価償却費と譲渡所得税の関連性
例えば取得価格2,000万円、累計減価償却800万円、売却価格1,500万円の場合、取得費は1,200万円となり、譲渡所得は300万円ではなく、実質300万円+800万円相当の利益と扱われる点がポイントです。
所有期間別の減価償却費と譲渡所得税のシミュレーション
所有期間が5年以下のケース
短期譲渡所得として39.63%の税率が適用されます。減価償却累計額は少ないものの、税率が高いため売却タイミングを慎重に選びましょう。
所有期間が5年超のケース
税率が20.315%に下がるため、長期保有メリットが生まれますが、累計減価償却が増えるため取得費が下がります。税率低下と取得費減少のどちらが有利かシミュレーションが不可欠です。
所有期間が10年超のケース
自宅売却なら軽減税率(14.21%)や3,000万円特別控除と併用でき、手取りが大幅に改善します。当社は売却価格・耐用年数・控除特例の三軸で最適な年内・翌年売却の比較を行い、節税効果を提示しています。 -
不動産売却後の譲渡所得税に利用できる控除・特例
マイホームの買い換え特例
売却益を繰り延べられる制度ですが、将来の買い換え先売却時に課税が繰り延べ分と合算されるため、資金繰りと相続対策を併せて検討する必要があります。
居住用財産譲渡時の3,000万円特別控除
確定申告で適用すれば、譲渡益から最大3,000万円を差し引けます。減価償却後の取得費が小さい場合でも、控除で課税ゼロになるケースが多く、自宅売却では最重要です。
マイホーム売却時の軽減税率
所有期間10年超かつ譲渡益6,000万円以下部分に14.21%が適用されます。特別控除との併用で実効税率が大幅に下がります。 -
不動産売却時の注意点とよくある質問
不動産売却時に注意すべきポイント
・売買契約成立日と引渡日の属する年で税率が変わる
・リフォーム費用を資本的支出として取得費に加算できるか修繕費として経費にするかで税額が変動する
・相続取得の場合は被相続人の取得費と減価償却累計額を引き継ぐ
減価償却に関するよくある質問
Q. リフォーム直後に売却する場合、減価償却はどう計算される?
A. 資本的支出として増加した取得価額は、残存耐用年数で月割計算した減価償却費を控除します。Q. 青色申告していない自宅でも減価償却は必要?
A. 必要です。税法上のみなし減価償却を計算します。
リフォーム・改修費と減価償却の関係:売却時の影響を解説
資本的支出と修繕費の分岐点
屋根の葺き替えや増築は資本的支出として取得価額に上乗せし、減価償却の対象となります。一方、クロス張替えのような原状回復は修繕費としてその年の経費となり、売却時の取得費には加算できません。びわこホームでは改修工事ごとに資本的支出判定書を作成し、税務署への説明資料としてご提供しています。 -
まとめ
税務調査で見落とされがちな減価償却のチェックポイントと対策
記帳ミスの典型例
耐用年数の取り違え、償却率の誤入力、改修費の資本化漏れが代表的です。当社は固定資産台帳と領収書を突合し、疑問点を事前整理して自主的に更正の請求を行うことで、延滞税を最小限に抑えたケースがあります。
相続後の不動産売却における減価償却の計算と適用特例
相続取得費加算の仕組み
相続税を納付してから三年以内に売却すると、相続税の一部を取得費に加算できます。相続不動産の売却では、被相続人の保有期間と減価償却累計額を引き継ぐため、事前に過去の申告書を確認しないと誤差が生じます。びわこホームは相続税申告書のデータを読み解き、取得費加算と減価償却の双方を反映した譲渡所得試算を行います。
不動産売却における減価償却の重要性の再確認
減価償却は売却前の節税と売却後の納税額を決定づける二面性を持ちます。建物の構造、耐用年数、改修履歴、所有期間、相続の有無――これらを正確に把握しなければ、思わぬ税負担が発生します。
びわこホームが提供するサポート
地元甲賀市に根差すびわこホームは、不動産売却の仲介はもちろん、減価償却の累計確認、譲渡所得税の試算、相続税との連携シミュレーションまでワンストップで対応します。売却を検討し始めた段階でご相談いただければ、最適な時期・手続きをご提案し、手取り額を最大化するお手伝いが可能です。
売却後に「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔しないために、まずは無料相談で現在の物件情報と将来のご計画をお聞かせください。地域を愛し、地域に育てられたびわこホームが、あなたの不動産売却を最後まで伴走いたします。